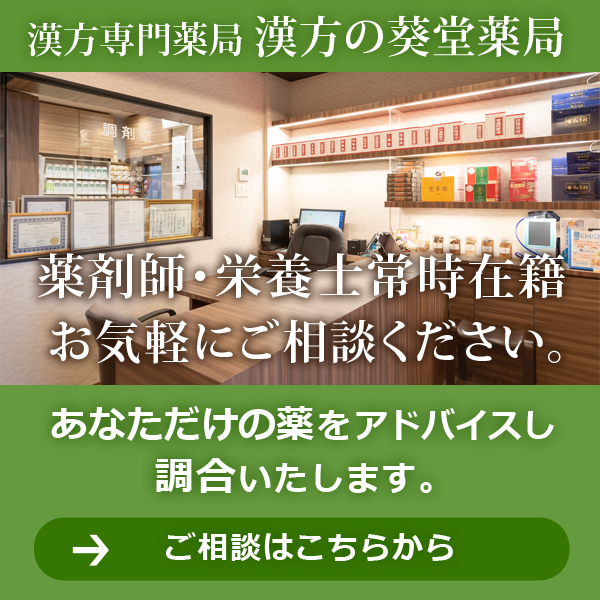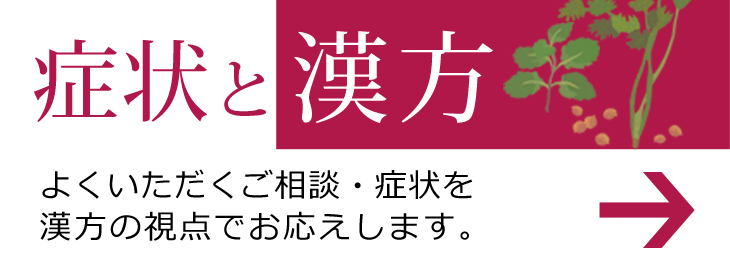副鼻腔炎(蓄膿症)と漢方
蓄膿症は昔からいわれている俗名で、医学的には副鼻腔炎といいます。こちらの呼び名の方が馴染みがあるという方も多いかもしれません。副鼻腔炎はアレルギー性鼻炎や花粉症の増加に伴い、増えているといわれています。そして、花粉症の低年齢化が進んでいることもあり、副鼻腔炎に関しても同様に低年齢化が進行しているようです。 副鼻腔ってどこにあるの? 副鼻腔炎という病名から「副鼻腔」に炎症を起こす病気ということは分かります。では「副鼻腔」とはどこにあるのでしょう。 鼻の周囲、頬・目の周りの空洞になっている部分のことです。その空洞は、鼻のすぐ横、頬のあたりに「上顎洞(じょうがくどう)」、目の間のあたりに「篩骨洞(しこつどう)」、おでこのあたりに「前頭洞(ぜんとうどう)」、鼻の奥深くに「蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)」、これが鼻を囲むように左右合計8個あります。 鼻腔(鼻の穴)や上記の副鼻腔の粘膜は繊毛という細かい毛で覆われ、外から入ってきたホコリ・花粉、ウイルスなどの異物を鼻水とともに排出し、異物が入らないよう体を守っています。もともと体に備わっているフィルターのような役目をしている場所といっても良いでしょう。 副鼻腔炎(蓄膿症)の原因は? 副鼻腔炎は、原因となる異物が上記の副鼻腔まで侵入し、炎症が起き、膿が発生した状態をいいます。その原因は、風邪などのウイルスが原因の「感染性」と、ハウスダストなどが原因の「アレルギー性」があります。そして、歯の根の先部分が副鼻腔の「上顎洞(じょうがくどう)」のすぐ側にあるため、虫歯や歯周病が原因で起こる場合もあります。 また、アレルギー疾患と慢性副鼻腔炎の合併率は30~40%との報告があり、この数値はアレルギー性鼻炎や花粉症の低年齢化が進んでいることからも、今後ますます増加していくと考えられています。文部科学省の学校保健統計調査でも、幼稚園や小学生の副鼻腔炎患者が増えているとの結果を発表しています。 副鼻腔炎(蓄膿症)の症状って? 副鼻腔炎の症状の中に、鼻がつまる・鼻水が出るというものがあります。これは、風邪やアレルギー性鼻炎とも同じです。しかし、副鼻腔炎になると、鼻は鼻腔(鼻の穴)から外に出るばかりでなく喉の方にも流れます。これを鼻後漏(こうびろう)といいます。外に鼻水が出るアレルギー性鼻炎とは対照的な症状です。 その他の症状としては、頭重・頭痛、口臭、顔や歯そして目の周辺の痛み、嗅覚・味覚障害、胃の不調、中には肩こりを訴える方もいらっしゃいます。また、集中力に欠け、情緒不安定でイライラしやすいといった精神的な症状も出てきます。鼻の病気で、鼻のみに症状が現れると思われがちですが、肉体面・精神面にも、予想する以上に広範囲に症状が出る病気だということが分かっていただけたと思います。 急性と慢性の違いは? 副鼻腔炎の原因でもっとも多いのが、風邪やインフルエンザのウイルスや細菌による感染です。 風邪などの時に鼻の穴の粘膜が腫れると、その奥にある副鼻腔の入口が塞がります。すると、空気の流れが悪くなり、副鼻腔の中の圧力が変化し痛みが生じることがあります。さらに、副鼻腔内が細菌感染すると、濃い鼻汁、発熱、さらに痛みが増すこともあり、こうした段階を「急性副鼻腔炎」といいます。 急性副鼻腔炎が目に近い副鼻腔で起こると、視覚異常が生じる場合があります。もし鼻汁など鼻に関わる症状だけでなく、目に何らかの異常を感じたときは、すぐに医療機関を受診する必要があります。 それに対して、慢性副鼻腔炎では痛みはほとんどありません。鼻汁が出る、鼻がつまる、匂いが分かりにくい、体がだるいといった症状です。このような症状のため風邪やアレルギー性鼻炎などと区別が付きにくく、放置している方も多いかもしれません。しかし、上記のような症状が1カ月以上続くときは、慢性副鼻腔炎の可能性が高いです。耳鼻咽喉科などを受診して検査を受け、適切な治療を受けましょう。 鼻腔および副鼻腔の炎症による症状の持続期間が4週間未満であれば「急性」、4~12週であれば「亜急性」、12週以上であれば「慢性」といわれています。また、急性鼻副鼻腔炎の殆どが7~10日で治癒するのに対し、慢性副鼻腔炎は長期的な治療が必要となります。 「急性副鼻腔炎」と「慢性副鼻腔炎」の症状の比較 急性副鼻腔炎 慢性副鼻腔炎 膿のような黄色い粘りのある鼻水が出る 頭が重く、集中力がなくなる 後鼻漏がある 鼻がつまる 頭痛や頬、眉毛、上顎の歯が痛む 鼻茸(はなたけ)という炎症性ポリープができてさらに鼻がつまる 鼻の中が臭い 後鼻漏のために慢性的な咳、喉に不快感がある 発熱することもある 嗅覚障害 稀に目や脳に進展してしまうこともある 鼻の中が臭い 好酸球性副鼻腔炎って何? 好酸球性副鼻腔炎は、慢性化のう性副鼻腔炎と比べて治りにくいとされ、2015年3月に難病指定された慢性副鼻腔炎の一つです。「好酸球」とは白血球の一種で、アレルギーの病気を起こした時に増える細胞です。アレルギーが原因で副鼻腔に炎症が起こり、この好酸球が副鼻腔にたくさん集まると好酸球性副鼻腔炎になります。 その症状としては、糊のような粘り気のある鼻水が出ることです。多くの場合、臭いを感じる細胞がある場所の近くにある副鼻腔を中心に炎症を起こすため、嗅覚障害を起こしやすいです。さらに、鼻茸と呼ばれる鼻ポリープが多発します。これが大きくなったり、多発することで鼻づまりが悪化し、鼻で呼吸することが困難となります。この鼻茸は正常な鼻・副鼻腔の粘膜が腫れ上がったもので、癌化する恐れはありません。しかし、切除手術しても再発を繰り返すこともあります。 副鼻腔炎の検査ってどんなことをするの? 慢性副鼻腔炎には、以下のような6種類の中から、症状によって必要な検査を受けて診断されます。 (1)問診 いつ頃からどのような症状があるのかを確認します。鼻づまり、粘り気のある鼻水、後鼻漏、咳、嗅覚障害、頭痛、頬の痛みなどの症状の確認 (2)細菌検査 分泌物を採取し、どんな細菌が繁殖しているか検査します。 (3)内視鏡検査 鼻腔に鼻茸がないか確認します。 (4)画像検査 X線、CT(コンピュータ断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像)などを利用して、副鼻腔の中の状態を確認します。 (5)血液検査 「好酸球性副鼻腔炎」が疑われる場合に行います。アレルギーの有無や、白血球の中の「好酸球」が過剰に増えていないかを調べます。 (6)嗅覚検査 タイプに関わらず受ける検査です。嗅覚検査には「静脈性嗅覚検査」と「基準嗅力検査」の2つがあります。前記は、ニンニク臭のあるビタミン剤を注射して、吐く息で匂いを感知するまでの時間と、匂いの持続時間を調べる検査です。後記は、バラの花や納豆、桃など5種類8段階の匂いを嗅ぐ検査です。 西洋医学的な治療について 年間約30万人が発症するといわれている慢性副鼻腔炎のうち、90%の人は「保存療法(鼻腔内の洗浄と薬物療法)」で治療されています。マクロライド系抗菌薬を使い、炎症を抑えることで副鼻腔内がもとの状態に戻ります。しかし、この治療は薬の服用期間が長いため、肝機能異常といった副作用の懸念があるため、血液検査でチェックしていく必要があります。 残りの10%は「手術療法」になります。内訳は、上記のような薬で治らなかった人と、大きな鼻茸(鼻ポリープ)ができている人です。現在は、内視鏡による手術が主流で、骨を大きく削ったり、粘膜を根こそぎ取るようなことはありません。 内視鏡手術のメリットは、出血や痛みが少なく、術後の回復も早いことです。鼻茸や膿を吸引しながら細かく削り取る画期的な装置の開発により、手術時間は大幅に短縮できるようになりました。両側で約1時間半、そして入院期間も1週間ほどと負担のないものになっています。 手術後はマクロライド系の抗生物質を少量長期投与し、残った病変をしっかりと治すことがとても重要になります。医師の指示に従い、自己判断で薬を止めてしまわず、根気強く治療を続けることが完治に結びつきます。 日常生活で注意すること […]